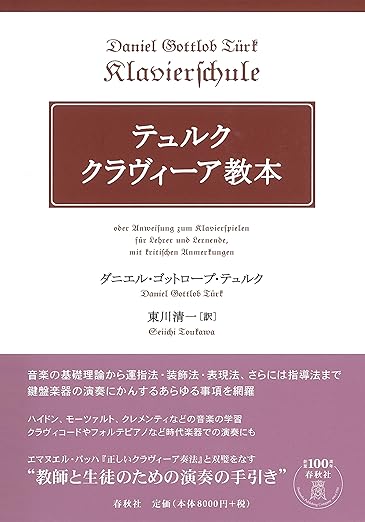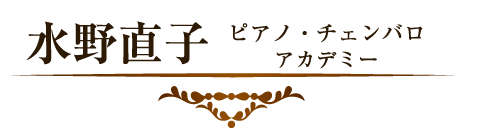速度標語のヒエラルキー:あなたの「アレグロ」は本当に「速い」だけ?
「Allegro(アレグロ)」を「速い」と訳すことは、実は少し危険な行為だったのかもしれません。しかし、すでにこの言葉が「速い」という意味で広く浸透してしまった今、それに抗うより、むしろこの「速さ」という観点から、クラシック音楽における速度のヒエラルキーを掘り下げてみよう、というのが今回のテーマです。
バロック倶楽部での授業の一部を紹介します。
よく使われる速度標語リスト(速い順)
こでは、特によく使われる速度標語を、速いものから順番に並べました。(もちろん、この他にも多くの標語が存在します。)
- Prestissimo(プレスティッシモ)
- Presto assai(プレスト・アッサイ)
- Presto(プレスト)
- Allegro assai(アレグロ・アッサイ)
- Molto allegro / Allegro di molto(モルト・アレグロ / アレグロ・ディ・モルト)
- Allegro non tanto(アレグロ・ノン・タント)
- Allegro non troppo(アレグロ・ノン・トロッポ)
- Allegro moderato(アレグロ・モデラート)
速度は作品の性格によって異なりますが、もし作品の性格を掴みかねている場合は、この速度標語が演奏のヒントを与えてくれることがあります。
ピアノ講師さんが驚く「他の楽器」の資料
私が他の楽器の資料を紹介することに驚かれるピアノ講師さんが多いのですが、バロック時代を振り返ると、その理由が見えてきます。
当時、装飾音の資料は「装飾音表」として残っていても、「楽器をどのように演奏するか」という具体的な奏法に関して、鍵盤奏者自身が書き記した文献は非常に少なかったのです。
その理由は定かではありませんが、18世紀中期から一気に出版された教本のうち、鍵盤奏者が残したものは、C.P.E.バッハとテュルクのくらい。他は、ほとんどが他の器楽奏者によるものでした。
中でも、クヴァンツの『フルート奏法』やレオポルト・モーツァルトの『ヴァイオリン奏法』は、当時の演奏習慣を知る上で、研究者にとってなくてはならない貴重な資料です。
よかったら、皆さんもぜひお手元に置いてみてください。何か疑問にぶつかった時、「もしかしたら、ここに書いているかも?」とページをめくってみると、きっと新しい、楽しい発見があるはずですよ。
参考資料
フルート奏法 https://amzn.to/4r2CXFG
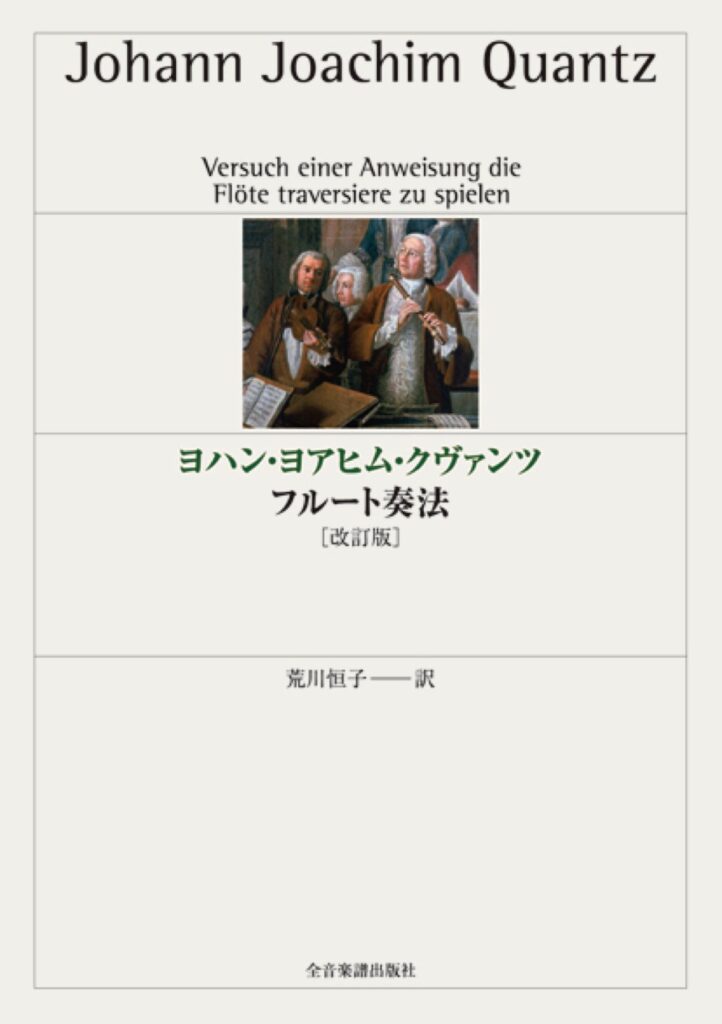
ヴァイオリン奏法 https://amzn.to/489wsJw
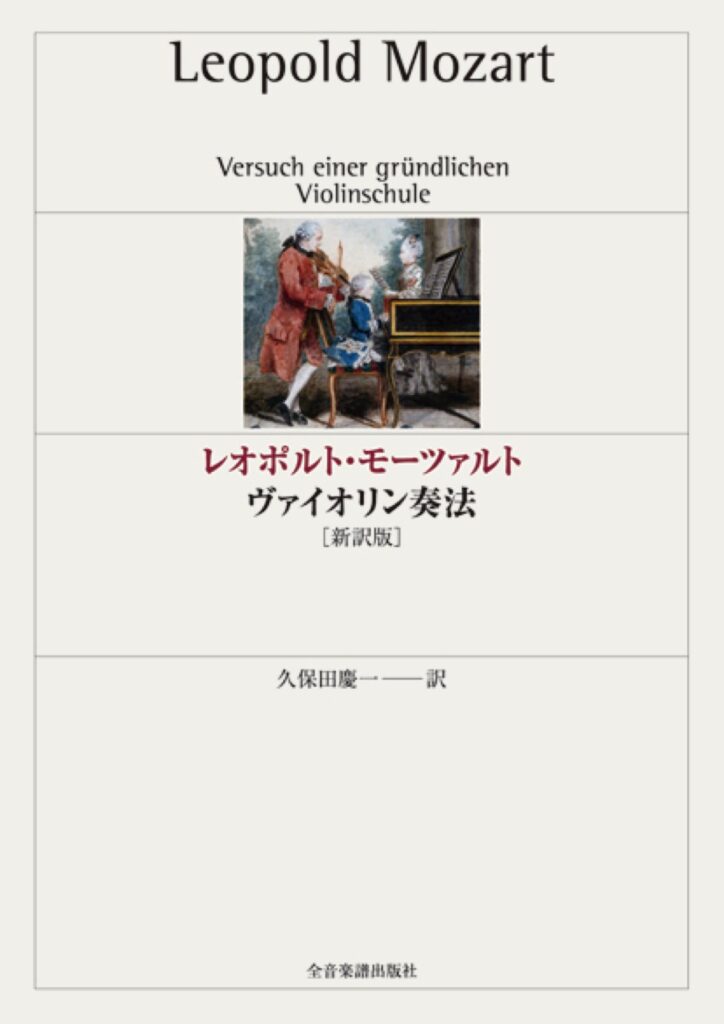
正しいクラヴィーア奏法 https://amzn.to/3LAsTU0
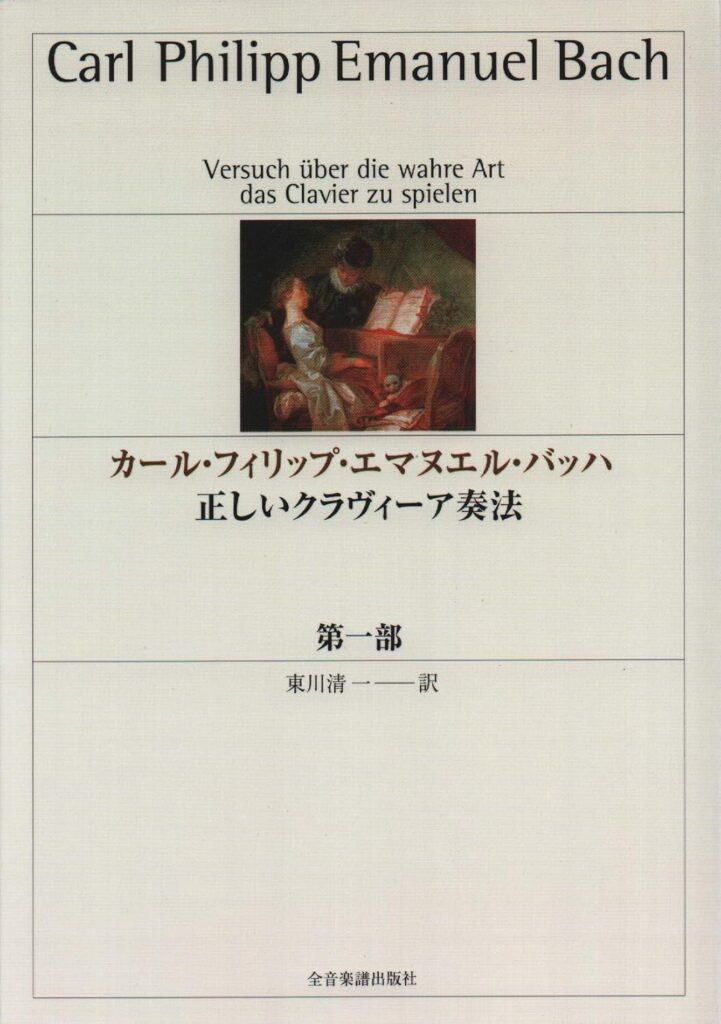
クラヴィーア教本 https://amzn.to/4pbKOio