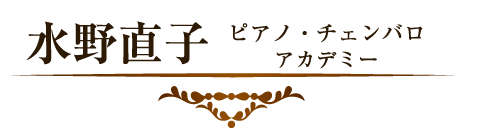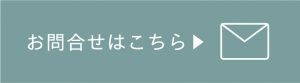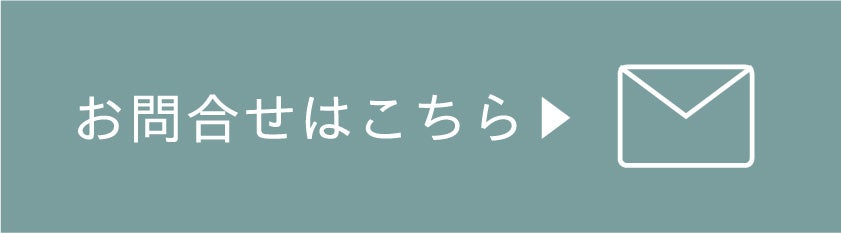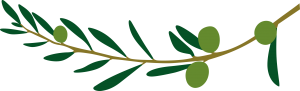親のサポートチェック項目
チェンバロ・ピアノ奏者 水野直子です。
「才能があるかわからないから」
「いつまでピアノをするかわからないから」
というお母さんへ。
子どもが習っているピアノが上手くなるかどうか気になるのは
親として当たり前のことだと思います。
ところが、ピアノが上手くなるためには
生まれながらの才能がなければならないのか、
というと
実はそうではないことの方が多いのです。
親が真剣に、子どものピアノをサポートしているか、
これこそが大切なことだと思います。
才能があれば、
親が何も言わなくても一人でピアノに向かうのか、
と思ったら大違いです。
モーツァルトも、ベートーヴェンも、
子どもの頃はピアノを弾かなくて
父親に叱られた経験を持っています。
今は、ゲームにテレビ、ネット環境が蔓延していて
ただ座っていさえすれば、
耳や目から勝手に情報が流れてくる、
楽で、誘惑の多い時代です。
こんな時代だからこそ、
親のサポートが
子供の未来を大きく左右すると私は思っています。
それでは前回で少しお話ししたチェック項目を発表します。
どれだけ当てはまるか、数えてみてください。
現在のピアノに対する(お子さんに対する)スタンスが現れてくると思います。
![]()
【ピアノの扱い方】
- ピアノの上に物が置いてある
- ピアノの上に楽譜が積み上げられている
- ピアノの椅子がピアノの前にない
- 足台がない
- 足台はあるがペダル付きの足台ではない
- ピアノを弾き終えても蓋を閉めないままで放置している
- ピアノを磨かない
- ピアノの上に水が入ったコップを置いたことがある
- ピアノの音が合っているのか狂っているのかわからない
- ピアノの調律の意味を知らない
- ピアノの調律を2年以上していない
- ピアノの調律をいつしたら良いか知らない
- ピアノの鍵盤を押しても音が鳴らない箇所がある
- ピアノを家族の入らない部屋に置いている
- ピアノを廊下など、通路スペースに置いている
- ピアノを寝室に置いている
- ピアノに虫やネズミが住むことを知らない → 1
【ピアノ教室・先生に対して】
- 先生のフルネームを知らない
- 先生のプロフィールを知らない
- 子どものピアノの先生とは挨拶程度
- 子供が体調不良でも月謝が勿体無いのでレッスンには連れていく
- 月謝を少しくらい滞納しても個人教室なら融通がきくと思っている
- 振替は当然だ
- 発表会は会費が高いので出させない
- 発表会の必要性を感じない
- 子どもが辞めたいと言ったらその時点ですぐに辞めさせるつもりだ
- ト音記号やヘ音記号を知らない
- どこへ行ってもピアノ教室なら全部同じ
- レッスン教材は中古で良い
- ピアノはそもそも高いので、教室も月謝で選ぶ
- レッスンに下の子を連れていく
- 先生のレッスンを見たことがない
- 子どもが先生に叱られたら腹が立つ
【家の練習で】
- 子どもの練習をゆっくり聞いてあげたことはない
- 1週間のうちに子どもがどのくらい練習したのかを知らない
- なんの教材を使っているのか知らない
- 子どもに「練習しなさい」と言っている
- 練習は子どもがピアノ好きなら一人で勝手にやるものだと思っている
- 子どもが弾けない時ついイライラしてしまう
- 子どもにレッスンをする
- 子どもが間違っているところをすぐ訂正してあげる
- 譜読みはいつも手伝っている
- わからない、と言われたらすぐに教える
- 子どもの演奏にはいつも褒める
- 子どもの演奏に感想を言ったことがない
- 練習の時間帯を決めていない
- 練習はしないがレッスンに行くのが楽しそうなので、それで良しとしている
- 練習しない子どもに、なぜ練習しないかをたずねたことがない
- レッスンのあった日に、どんなレッスンを受けたのか聞かない
- レッスンの前や練習前に親子喧嘩をする
- 飴やガムなど、おやつを食べながら練習している
- ピアノを弾く前に手を洗ったり爪を切ったりする声がけをしない
- 子どもの練習は、家族の団欒場所で行っている
- 子どものピアノの練習時にテレビがついている
- 別の兄弟が練習の邪魔に入っても注意しない
全部で55項目あります。
お時間のあるときにチェックしてみてくださいね。
![]()
チェックが5以下の場合は、立派なサポーター。
お子様もお母さんとの意思疎通ができて、安心してピアノを続けていけます。
音楽のこともご存知と思いますので
これからお子様と一緒にもっと音楽を楽しんでくださいね。
チェックが6〜10までの方も頑張っていますが、あともう少し。
お子様は、自宅での練習にもう少し優しい言葉がけや、もう少しかまってほしい、と思っているかもしれません。
ピアノに対して悩みがないか、話し合う時間を作るといいかも。
チェックが11〜20個の方は、良かれと思っていることがお子様には逆効果かも。
それ以上の方は、ピアノ教育についてもう一度考える必要がありそうです。
ピアノは、ピアノ教室へ行っていさえすれば身につくものではありません。
お子様と一緒にピアノを勉強していく、という意識や覚悟を持ってピアノへ臨みましょう。
子どもは親の姿勢を見て大きくなります。
大人がピアノに親しみ、楽しんでいる様子を見せることが大切です。
子どもを変えたい、と思ったらまずは自分が変わることから。
そうして初めて子どもも変わっていくということを再認識してください。
体験レッスンの流れはこちらをご参考ください。
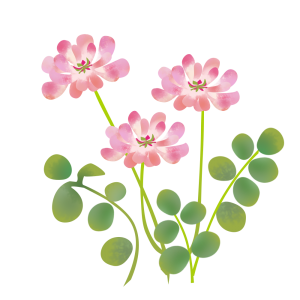
YouTubeにて教室の様子がご覧いただけます。
教室は「導入期」の指導を大切にしています。
「楽しい」の先にある、上質な音楽教育を目指します。
教室紹介動画
ピアノ指導者を対象にバロック指導を行っています。
バロック音楽の難しさは
楽譜に記されていない大切な情報を
正確に読み込むことにあります。
アーティキュレーションのつけ方
装飾法
強弱のつけ方など 全てに理由があり
自己流は誤演奏となり兼ねません。
バロックの基礎的知識を養いたい方
楽譜の読み方
インヴェンションやシンフォニアをはじめ
平均律をもう一度勉強したい方をはじめ
バロック演奏のタッチ
指導法 など
様々なニーズに対応しています。
またPTNA登録のセミナー講師としても活動しています。